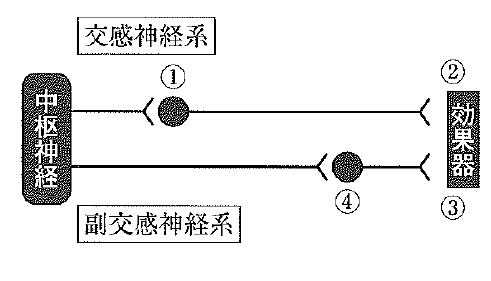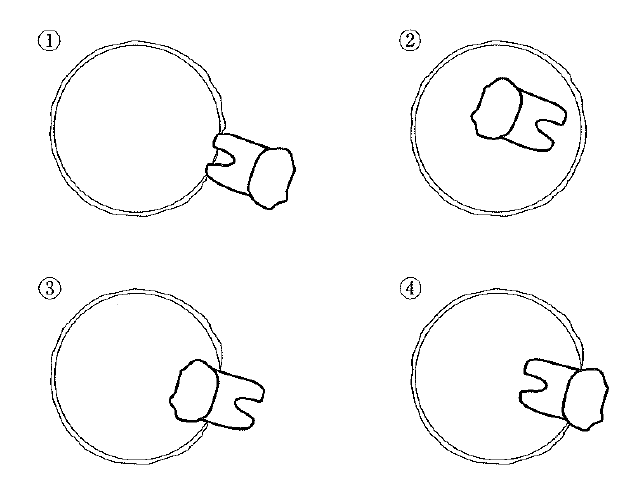疾病の成り立ち及び回復過程の促進の過去問
第25回午前:第15問
歯質変色の副作用がある薬物はどれか。
1: アモキシシリン
2: セファレキシン
3: テトラサイクリン
4: クラリスロマイシン
- 答え:3
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第24回午後:第8問
慢性炎症時に出現し、抗体を産生するのはどれか。
1: 好中球
2: 形質細胞
3: マクロファージ
4: T細胞〈Tリンパ球〉
- 答え:2
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第24回午後:第9問
□に入る語句の組合せで正しいのはどれか。エナメル質の初期う蝕には□がみられ、さらに進行すると□が起こる。
1: 表層下脱灰/再石灰化
2: 表層下脱灰/実質欠損
3: 生活反応層/再石灰化
4: 生活反応層/実質欠損
- 答え:2
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第24回午後:第10問
波動を触れる腫瘤の写真(別冊午後 No.2)を別に示す。腫瘤の主体をなす病理組織所見はどれか。

1: 骨形成
2: 粘液貯留
3: 角化物〈角質物〉
4: メラニン色素沈着
- 答え:2
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第24回午後:第11問
多剤耐性細菌のグラム染色像の写真(別冊午後 No.3)を別に示す。考えられるのはどれか。
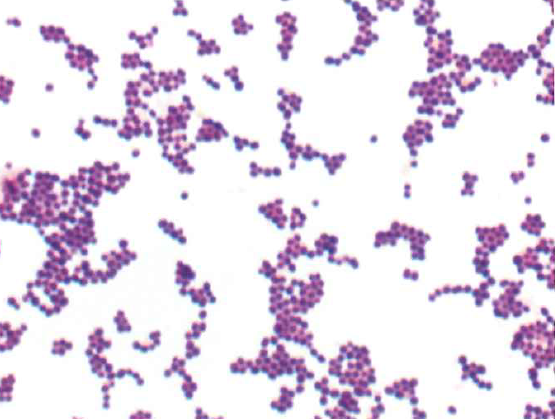
1: Escherichia coli
2: Mycobacterium tuberculosis
3: Pseudomonas aeruginosa
4: Staphylococcus aureus
- 答え:4
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第24回午前:第9問
歯内腫瘍の病理組織の模式図を示す。黒塗りは腫瘍細胞の分布を示す。この腫瘍はどれか。
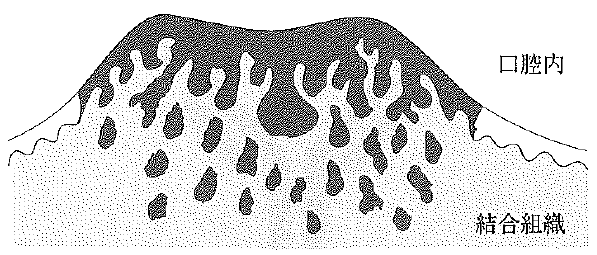
1: 乳頭腫
2: 線維腫
3: 線維肉腫
4: 扁平上皮癌
- 答え:4
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第24回午前:第10問
歯牙腫で正しいのはどれか。
1: 高齢者に好発する。
2: セメント質は含まれない。
3: 歯の萌出障害の原因となる。
4: 顎骨を破壊して浸潤増殖する。
- 答え:3
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第24回午前:第12問
抗体〈IgG〉の基本構造の模式図を示す。矢印が示すのはどれか。
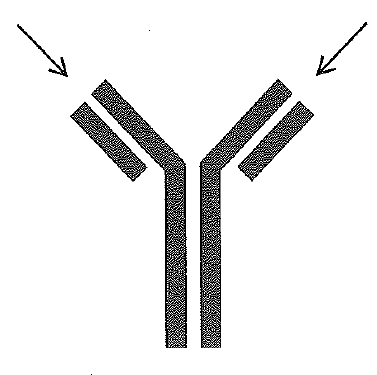
1: ヒンジ部
2: 抗原結合部
3: 補体結合部
4: Fcレセプター結合部
- 答え:2
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第24回午前:第13問
薬剤感受性試験の拡散法〈感受性ディスク法〉の写真(別冊午前 No.1)を別に示す。矢印で示した黒丸は薬剤を含んだディスクである。最も効果のあるのはどれか。
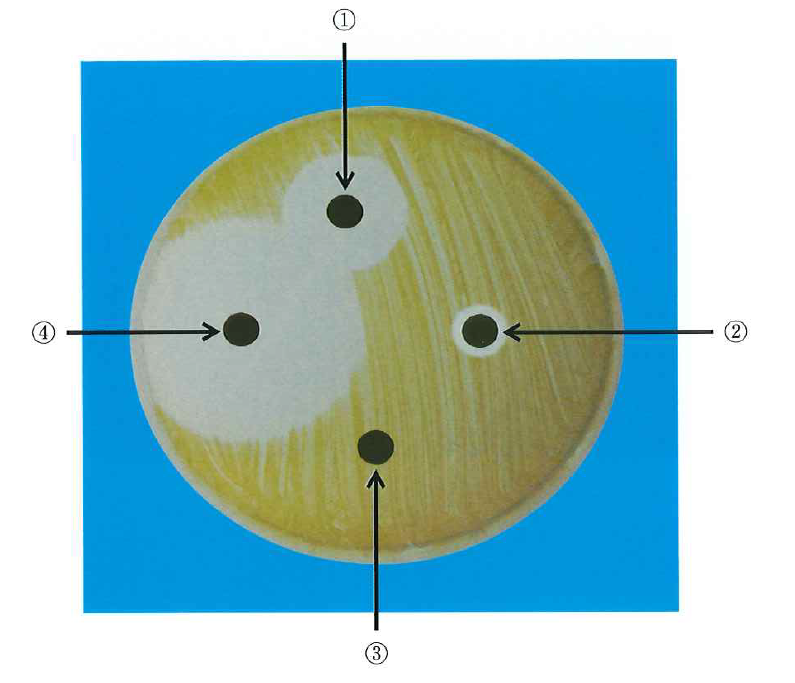
1: ①
2: ②
3: ③
4: ④
- 答え:4
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第24回午前:第14問
ロキソプロフェンナトリウムが阻害するのはどれか。
1: コリンエステラーゼ
2: シクロオキシゲナーゼ
3: トランスペプチダーゼ
4: ホスホジエステラーゼ
- 答え:2
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第24回午前:第15問
薬物を経口投与と静脈内投与したときの血中薬物濃度-時間曲線を図に示す。斜線部面積と点状部面積の2つの比から求められるのはどれか。
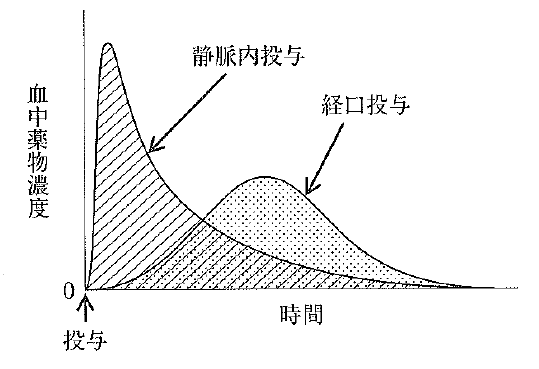
1: 分布容積
2: 生物学的利用能
3: 生物学的半減期
4: 全身クリアランス
- 答え:2
- 類似問題を見る
- この問題について報告する