第31回午後第91問の類似問題
第30回午前:第20問
歯周病の第二次予防はどれか。2つ選べ。
1: 歯周病検診
2: 食生活指導
3: 歯周外科治療
4: 口腔機能回復治療
- 答え:1 ・3
- 科目:歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第24回午前:第61問
摂食嚥下障害患者に対する機能訓練の口腔内写真を示す。 目的はどれか。
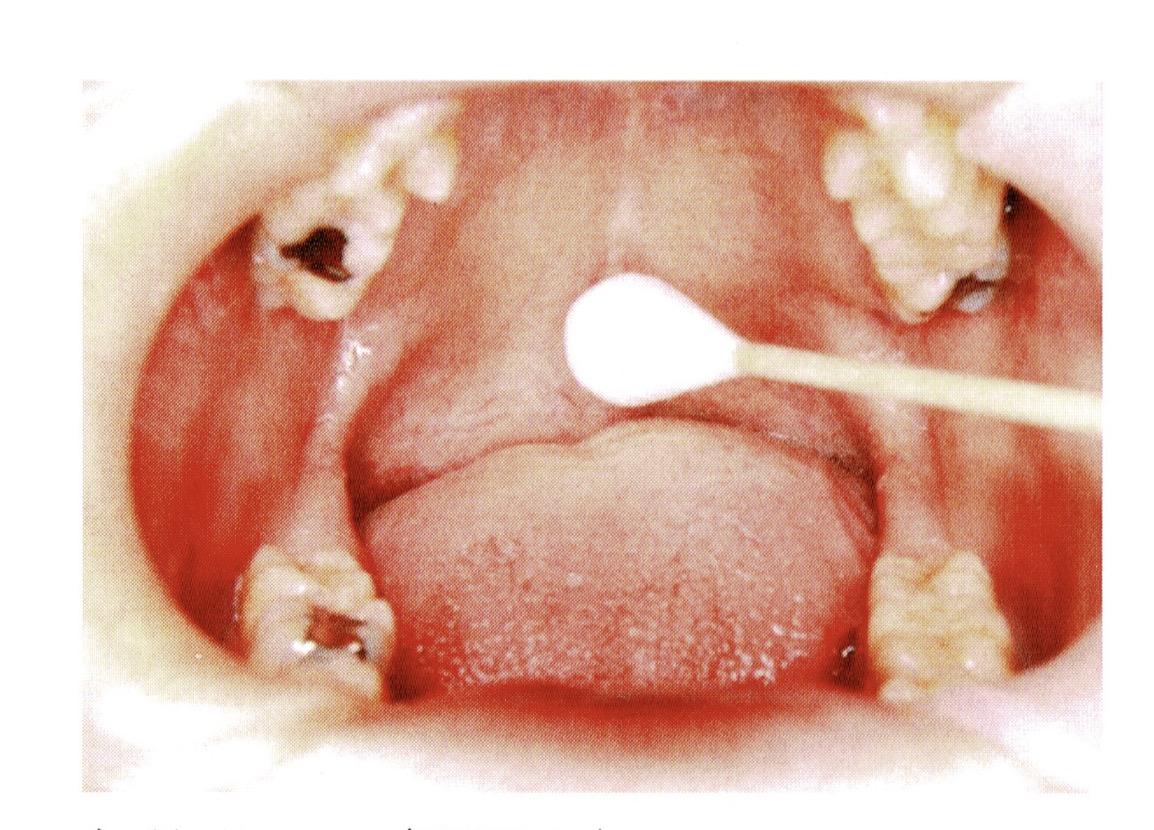
1: 声帯の内転強化
2: 唾液分泌の抑制
3: 嚥下誘発の感受性の向上
4: 舌骨を挙上する筋の筋力増強
- 答え:3
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第29回午後:第93問
摂食嚥下障害に対して上顎に装置を製作した。装置の写真(別冊午後No.32)を別に示す。改善できるのはどれか。1つ選べ。
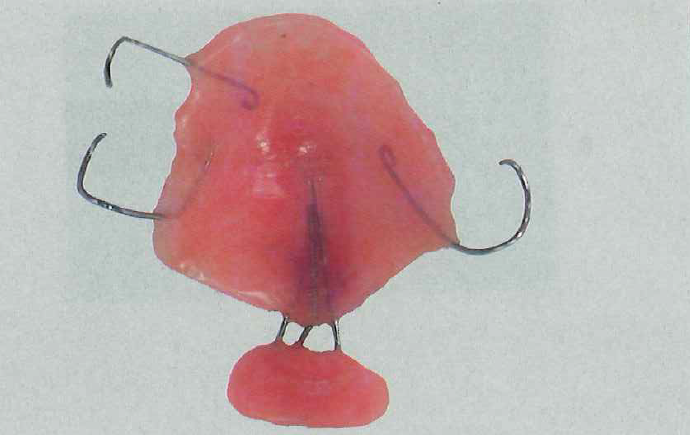
1: 口唇閉鎖不全
2: 舌骨挙上不全
3: 鼻咽腔閉鎖不全
4: 食道入口部開大不全
- 答え:3
- 科目:歯科保健指導論
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第26回午後:第89問
7歳の女児。小学校での保健指導で担任から相談を受けた。女児は給食で口にした食物を詰め込むことが多くなり、何度か窒息しそうになったという。全身疾患は特に無い。口腔内写真(別冊午後No.20)を別に示す。 担任に対する適切な助言はどれか。2つ選べ。

1: ペースト食に変更したほうが良いです。
2: 摂食嚥下の専門外来を受診すると良いです。
3: 歯科医院で子供用の入れ歯を作ると良いです。
4: 前歯が生えるまで食物を小さくして食べると良いです。
- 答え:2 ・4
- 科目:歯科保健指導論
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第26回午前:第88問
摂食嚥下リハビリテーションに関わる職種とその役割の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
1: 管理栄養士ーーー食事の介助
2: 作業療法士ーーー食器具の選定
3: 理学療法士ーーー筋緊張の調整
4: 言語聴覚士ーーー摂食嚥下機能の診断
- 答え:2 ・3
- 科目:歯科保健指導論
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第23回午後:第91問
ライフステージと口腔に現れやすい症状との組合せで正しいのはどれか。
1: 妊産婦期ーーー歯肉炎の軽滅
2: 学齢期ーーー唾液分泌量の減少
3: 青年期ーーー永久歯喪失の急増
4: 老年期ーーー歯根面う蝕の増加
- 答え:4
- 科目:歯科保健指導論
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第22回午前:第52問
矯正歯科治療で公的保険の給付対象となるのはどれか。2つ選べ。
1: 乳歯列期の下顎前突
2: 唇顎口蓋裂に伴う咬合異常
3: ダウン症候群に伴う咬合異常
4: 正中埋伏過剰歯に伴う咬合異常
- 答え:2 ・3
- 科目:臨床歯科医学
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第29回午後:第16問
摂食嚥下運動の流れの一時期を図に示す。この時期はどれか。1つ選べ。
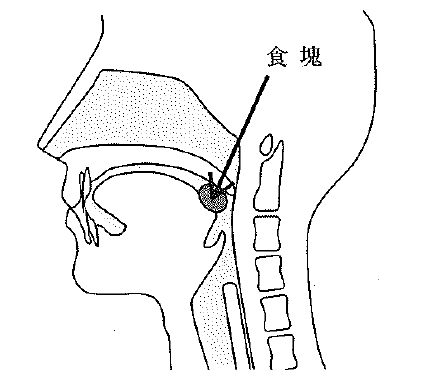
1: 準備期
2: 口腔期
3: 咽頭期
4: 食道期
第27回午後:第92問
76歳の男性。食後よくむせることを主訴として来院した。1年前に脳血管疾患を発症したという。摂食嚥下機能障害と診断され、リハビリテーションを行うことになった。 適切な代償的アプローチはどれか。
1: 食前に口腔周囲筋強化訓練を行う。
2: 摂食時の姿勢は45度仰臥位をとる。
3: 食物形態を噛みごたえのあるものにする。
4: 頸部の過伸展を防ぐためコップの縁を切る。
- 答え:2
- 科目:歯科保健指導論
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第27回午後:第60問
経鼻経管栄養の特徴として正しいのはどれか。2つ選べ。
1: 嚥下機能を阻害する。
2: 6週以上の留置が可能である。
3: 消化管粘膜の萎縮を予防できる。
4: 留置のための外科的手術が必要である。
- 答え:1 ・3
- 科目:臨床歯科医学
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第30回午後:第95問
摂食嚥下機能の獲得過程の項目を表に示す。正しい順序はどれか。1つ選べ。
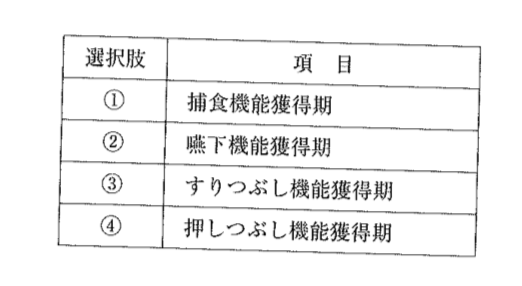
1: ①→②→③→④
2: ②→①→④→③
3: ③→④→①→②
4: ④→③→②→①
- 答え:2
- 科目:歯科保健指導論
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第27回午後:第83問
乳幼児期と保健管理の組合せで適切なのはどれか。2つ選べ。
1: 7〜8か月ーーー口の中を触れることに慣れさせる。
2: 1歳6か月ーーー指しゃぷりの習慣をやめさせる。
3: 3歲ーーー日常の歯磨きが自立する。
4: 5歲ーーー食生活を含めた口腔管理が必要になる。
- 答え:1 ・4
- 科目:歯科保健指導論
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第27回午後:第91問
80歳の男性。2週前に下顎全部床義歯を紛失した。上顎には14本の歯を有し、普段の食事の飲み込みには問題ないという。 摂食嚥下の過程で影響がある時期はどれか。
1: 先行期
2: 準備期
3: 口腔期
4: 咽頭期
- 答え:2
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第25回午後:第50問
嚥下機能の賦活を目的とするのはどれか。2つ選べ。
1: 舌負荷訓練
2: 喉頭挙上訓練
3: 義歯床のリライニング
4: ティッシュコンディショニング
- 答え:1 ・2
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第26回午後:第83問
67歳の男性。入院中の口腔衛生管理を行うことになった。食道癌の診断で2週間前より放射線治療と化学療法を行っており、4日後に手術が行われるという。口腔内の評価では、う蝕や歯周病は無かったが口が渇くと訴えていた。評価時の舌の写真(別冊午後No.17)を別に示す。 歯科衛生士が行う口腔衛生管理によって期待される効果はどれか。2つ選べ。
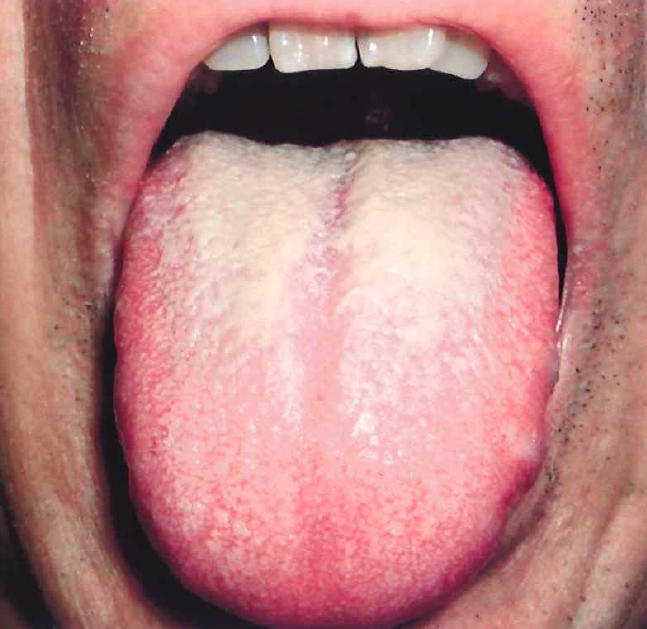
1: 入院期間の短縮
2: 原発病巣の縮小
3: 創部感染の予防
4: 安静時唾液の増加
- 答え:1 ・3
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第29回午後:第81問
乳児の保護者に対する適切な口腔保健指導はどれか。2つ選べ。
1: 授乳方法
2: 口腔習癖の指導
3: フッ化物洗口の推奨
4: 乳歯の萌出時期の説明
- 答え:1 ・4
- 科目:歯科保健指導論
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第28回午前:第95問
3歳の男児。脳性麻痺があり食事の際に過開口になり、スプーンを咬んだり、食べこぼしもみられる。まず獲得すべき摂食機能はどれか。
1: 捕食機能
2: 自食機能
3: 押しつぶし機能
4: すりつぶし機能
- 答え:1
- 科目:歯科保健指導論
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第22回午後:第102問
介護保険制度で、介護予防対象者への口腔機能向上サービスを担当する専門職種はどれか。2つ選べ。
1: 歯科衛生士
2: 理学療法士
3: 介護福祉士
4: 言語聴覚士
- 答え:1 ・4
- 科目:歯科診療補助論
- 類似問題を見る
- この問題について報告する